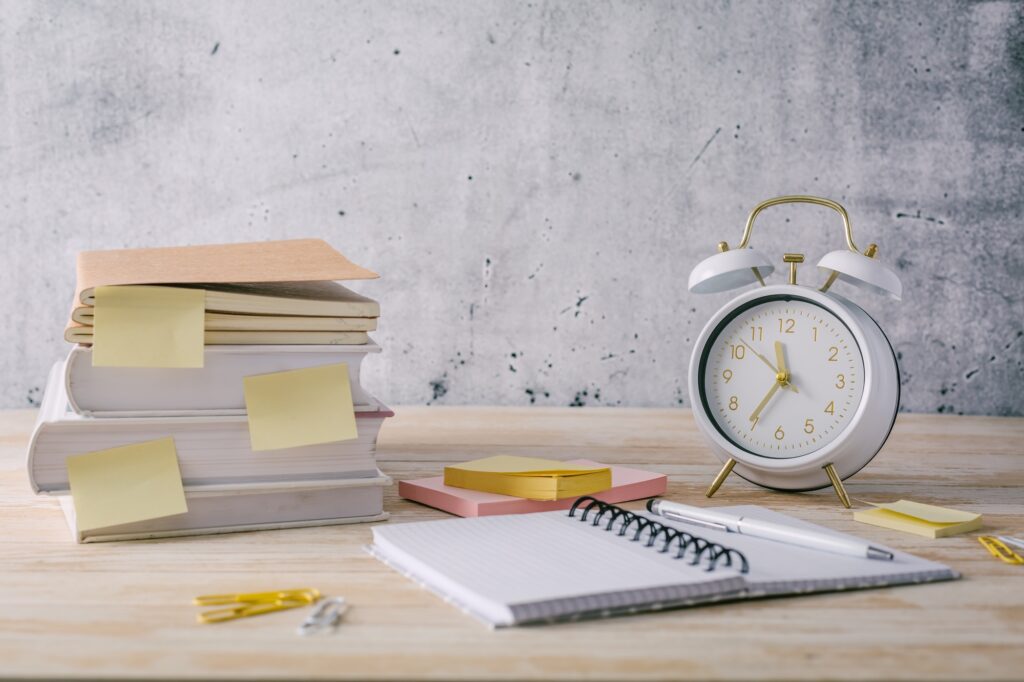今回は、限られたリソースを最大限に活用する方法について学びます。
- タイムブロッキング
- 優先順位の設定
- 外部リソースの活用
- 無料ツールの利用
効率的なリソース管理は、効果的な情報発信の鍵となります。まず、時間管理の重要性について説明します。時間を無駄にしないためには、計画的に作業を進めることが大切です。ここでは、具体的な時間管理の方法として、タイムブロッキングをご紹介します。
さらに、優先順位の設定、外部リソースの活用、無料ツールの利用を組み合わせることで、限られたリソースを効率的に活用し、情報発信の質と量の向上を図ります。
タイムブロッキングを取り入れる
タイムブロッキングで時間の使い方を変える
タイムブロッキングという言葉を聞いたことがありますか?
タイムブロッキングとは、一日のスケジュールをブロックごとに分けて計画する方法です。例えば、私の場合は午前9時から午後1時はコンテンツ作成、午後3時から4時はSNSのアイデア準備といった具合にスケジュールを設定しています。このように、あらかじめ時間を区切っておくことで、それぞれのタスクに集中しやすくなる、というメリットがあります。ここでは、タイムブロッキングの概念、そして、なぜそれが有効なのかという理由、さらに具体的な例について説明していきます。
タイムブロッキングとは、一日の時間を「ブロック」、つまり、ある程度まとまった「かたまり」に分けて、それぞれのブロックに特定のタスクや活動を割り当てる時間管理の方法です。スケジュール帳やカレンダーを使用して、具体的な時間帯に具体的なタスクを計画することで、計画的かつ効率的に時間を使うことができるようになります。この「かたまり」というところが重要なポイントです。
タイムブロッキングが有効な4つの理由
私はかつて「スキマ時間」を見つけて作業することが好きな人でした。スキマ時間の15分でタスク A をやって、次の30分でタスク B をやる……というふうに、かなり細かく分けてしまっていたので、一つ計画が崩れると芋づる式に他の予定も崩れてしまう、つまり、予定が総崩れになる、みたいなことがよく起こっていました。タイムブロッキングは、それよりも、もっと大きい「かたまり」で管理しようという、今までとは全く異なる考え方です。
タイムブロッキングが有効な理由は、主に4つあります。
集中力の向上
タイムブロッキングをすることによって、一度に一つのタスクに集中することができる環境を、半ば強制的に作り出すことになります。その結果、あれこれと気が散ってしまう、つまり、注意散漫になることを防ぎます。
時間の有効活用
タスクごとに時間を割り当てることで、無駄な時間を減らして、効率的に作業を進めることができます。「タスクごとに時間を割り当てる」というのは、一見すると当たり前のことに聞こえます。しかし、人間は、実際には一度に一つのタスクしかできないものです。ここで重要なのは、「割り込みを許さない」ということです。他のタスクや、突発的な用事、あるいは、ついつい見てしまう SNS などを、その時間には「絶対にやらない」と決めてしまうことが大切です。
例えば、私が先ほどお話ししたように、午前中の4時間をコンテンツ作成に充てると決めたら、その時間はコンテンツ作成しかやりません。その間に何か調べ物をしたり、SNS を見に行ったり、YouTube を見てしまったり、あるいは何かメルマガを書き始めたりするということは一切その間には発生させない、つまり、他のことをする時間は持たないようにします。そうすることで他のことに気を取られず、一つの作業に没頭できるのです。
そうすると、脳は、作業の切り替え(スイッチ)にエネルギーを使わなくて済みます。ずっと同じタスクを延々と続けていれば、「あ、そういえばあれどうだっけ」というふうに、他のことを自然と考えてしまうかもしれません。しかし、その切り替えのたびに、脳はすごく無駄なエネルギーを使ってしまいます。そして、また元のタスクに戻るときにもエネルギーを使うので、タスクを切り替えないほうが、結果的に時間を有効活用できるのです。一つの作業に集中することで作業効率が上がり、結果として時間の節約になります。
優先順位の明確化
タイムブロッキングでは、重要なタスクを優先してスケジュールに組み込むことができます。こうすることで、その日の活動において、優先順位を見失わずに作業を進められます。自分で言っていて耳が痛いのですが、本当にこの通り、時間を割り当てて優先順位通りに設定しておいて、そのルールを破るのを許さないというふうにすると、重要なタスクから着実に完了していきます。
ストレスの軽減
具体的な計画を立てることで、「タスクをやり終えられるかどうか」という不安を軽減し、精神的な余裕が生まれます。そう言うと聞こえがいいのですが、私の場合は、スキマ時間でやりくりしていたときは、とにかく時間内にタスクが終わりませんでした。15分や30分の単位で脳を切り替えようとしても、脳が切り替わって本当にタスクに入れるまでに、私の場合、たぶん5分ぐらいかかっていたと思います。
ということは、15分あったはずが、実際にタスクに取りかかれるのは10分だった、みたいなことが頻繁に発生していたわけです。そうすると、当然、タスクの積み残しが発生します。タスクを積み残してどんどんどんどん溜まっていくと、罪悪感や劣等感、自責の念など、いろいろなネガティブな感情に見舞われます。精神衛生上、非常によくない状態です。
そうではなくて、優先順位をつけてブロックとして時間を確保して、脳のスイッチを切り替えないようにすると、タスクは確実に片付いていくので、ストレスがなくなります。もちろん、私も計画通り、時間通りに終わらなかったりすることはあります。しかし、優先度の高いタスクがある程度ちゃんと前に進んでいく感覚は持てるので、スキマ時間でどうにかしようと考えて、あれこれと手を出して、結局どれも中途半端になってしまって、自己嫌悪に陥っていたあの頃よりはずっとストレスがありません。精神的な負担がずいぶん軽くなりました。
仕事の日のタイムブロッキング例
では、タイムブロッキングの具体例を見てみましょう。ここでは、仕事の日のタイムブロッキングを例に挙げます。
08:00-09:00:メールチェックと返信
※あまりお勧めではない始め方ですが、眠気の残っているときには、こういう軽いタスクを入れるのも良いでしょう。ご自身の集中力の高い時間帯がいつかを把握して、そこに重たい作業を当てていくのがお勧めです。
09:00-11:00:プロジェクトAの作業
11:00-12:00:チームミーティング(オンラインであるかもしれません)
12:00-13:00:昼食休憩
13:00-15:00:プロジェクトBの作業
15:00-15:30:休憩
15:30-17:00:クライアントへの報告書の作成
17:00-18:00:明日のスケジュール確認と調整
このように、ある程度まとまった時間、かたまりで区切ってタスクを実行していきます。
学習する日のタイムブロッキング例
次に、学習する日のタイムブロッキングです。
08:00-09:00:読書とノート取り
09:00-10:00:オンラインコースの視聴
10:00-10:30:休憩
10:30-12:00:課題の作成
12:00-13:00:昼食休憩
13:00-14:00:グループディスカッション(オンラインでやったりします)
14:00-15:30:プロジェクトの研究
15:30-16:00:休憩
16:00-17:00:まとめと復習
このように一日のスケジュールを俯瞰してみると、やることがとてもシンプルに見えてきませんか?
仕事と学習を日によって分けることが難しい場合は、仕事と学習を一日の中で同時に行うことになりますが、その場合は以下のようなタイムブロッキングになります。
仕事と学習を組み合わせたタイムブロッキング例
以下は、仕事と学習を組み合わせたタイムブロッキングの具体例です。例えば、平日6時に起きる人(私は6時には起きられませんが)は、以下のようにタイムブロッキングできます。
06:00-07:00:朝のリフレッシュ(運動や瞑想など)
07:00-08:00:朝食と準備
08:00-09:00:読書とノート取り(学習)
09:00-10:30:メールチェックと返信(急ぎのものは早く片付けるという考え方)
10:30-11:00:休憩
11:00-12:00:オンラインコースの視聴(学習)
12:00-13:00:昼食休憩
13:00-15:00:プロジェクトAの作業(仕事)
15:00-15:30:休憩
15:30-17:00:課題の作成(学習)
17:00-18:00:クライアントとのミーティング(仕事)
18:00-19:00:夕食休憩
19:00-20:00:見直しと提出(学習)
20:00-21:00:プロジェクトBの作業(仕事)
21:00-22:00:自由時間(リラックスしたり、趣味のことを行う)
22:00-23:00:明日のスケジュール確認と準備
23:00-:就寝準備
家事や育児などが入るときは、それらもできるだけブロックで実行します。これはあくまでも理想論ですが、できるだけブロックでやるという意識を持つだけで、時間の使い方が変わってきます。
タイムブロッキングを成功させるポイント:バランスを取る
上の例では仕事と学習の時間を交互に設定することで、集中力を維持しやすくしています。先ほど、「似たようなタスクをまとめて入れたほうがいい」と言ったことと矛盾しているように思われるかもしれませんが、同じ作業ばかりでは人間、誰しも飽きてしまいます。飽きを防いでちょっと気分転換を兼ねて作業を変更するというのも、一つの有効な方法です。
ここで気をつけていただきたいのは、学習と仕事を入れ替えはしていますが、30分ごととか15分ごとというような細かい区切りはしていないということです。15分でメールチェックをして、その15分後にオンラインコースの視聴という学習のモードに切り替えるとかいうことはしていません。ある程度まとまった時間で区切る、ということが大切です。
タイムブロッキングを成功させるポイント:休憩を取る
適度な休憩はやはり必要です。休憩を取ることで、疲れを軽減して、次のブロックの作業効率を上げることができます。
タイムブロッキングを成功させるポイント:柔軟性を持つ
ここではあまり余白を取っていませんが、そもそも大きく時間帯をかたまりで取っているということ自体、柔軟性を持たせることができるということです。つまり、突発的な出来事や、急な予定変更にも対応できる、ということです。
前のタスク管理ツール説明動画で、私のNotionを見ていただいたときに、日曜日にほとんど予定が入っていないことにお気づきだったかと思います。日曜日は完全にオフかと言うと、そうでないこともあります。あの日はバッファ、いわば予備の時間として確保してあるのです。
サラリーマンのときは土日に確実に休むということができていました。もちろん、学会に行ったりとか勉強会に行ったりとか、あるいは、場合によっては、自宅で学習することもありました。しかし、基本的にサラリーマンのときは土日休みでしたが、個人事業主になってからはそこまでがっつりと休むことはなかなか難しいものです。なので、休みの日は確保はしておくのですが、仕事がちょっと後ろ倒しになってきてしまったなというときは、日曜日にその予備時間を使って調整するというふうに、余裕を持たせています。
タイムブロッキングを成功させるポイント:セルフケア
朝と夜の時間にセルフケアを行うことで、心身のリフレッシュを図ります。私の事例ではないので書いていませんが、適度な運動や、あるいは人によっては、昼寝が有効な人もいます。
自分のコンディションや自分のペースに合わせて仕事ができるというのが個人事業主の特権ですから、しっかりとセルフケアも行いながらリフレッシュして、生産性を下げないように工夫する、というのも有効だと思います。
タイムブロッキングを試してみよう
このようなスケジュールを参考にして、ご自身の生活リズムや優先順位に合わせて、タイムブロッキングをカスタマイズしてみてください。
タイムブロッキングだけでなく、習慣を変えるには少なくとも3ヶ月かかると私は感じています。まずは3ヶ月、試しにやってみて、その3ヶ月の間にいろいろな気づきがあって、ご自身でアレンジをしたりチューニングをしたりすることになるでしょう。そうして、だんだんと「自分はこの感じでやっていけばよさそうだ」というのが見つかってくるのが、3ヶ月目ぐらいだと思います。
ぜひ一度、タイムブロッキングを試してみてください。
副業にタイムブロッキングをどう組み込むか
実業で成功している方が、副収入としてオンラインコースを作成する時間を一日のなかでどう組み込むのかというと、本業の合間にオンラインコースの構成案を作成したり、コンテンツ作成をしたり、あるいは編集作業をしたりというふうに入れていくことになります。これは、先ほど説明した「学習と仕事の切り替え」と似ています。
タイムブロッキングは、計画的に時間を使い、効率的かつストレスなく作業を進めるための強力なツールです。タイムブロッキングだけで1つの書籍が出版されているというのが、英語圏ではよくあります。それぐらい、このタイムブロッキングという考え方は、幅広い、柔軟な概念なのです。最初は慣れないかもしれませんが、続けることで効果を実感できるようになります。時間の管理がうまくなることで、日々の生活や仕事がより充実したものになります。
また、ここでは情報発信の話をしていますが、どうしても途切れがちな情報発信の作業を確実にこなしていくことができるようになります。ぜひお試しください。
優先順位を設定する
優先順位の設定
タスクに優先順位を設定することで、重要な作業を最優先で進めることができます。次の手順で優先順位を設定します。まず、全てのタスクをリストアップしてタスクリストを作成します。そして次に重要度と緊急度を評価します。それぞれのタスクの重要度と緊急度を評価して、4つのカテゴリに分類します。これについては後で述べます。優先順位を設定します。重要かつ緊急なタスクを最優先で取り組み、次に重要だが緊急ではないタスクを進めるということです。
重要度と緊急度の評価、削除対象
どこかで見たことがあるなという図が出てきました。アイゼンハワーマトリクスの4つの領域といわれています。
横軸が緊急か緊急ではないか、縦軸が重要度です。重要度が高いか重要度が低いかということです。そして、緊急かつ重要度が高いというものは、期限や影響が大きいタスクです。期限があって影響が大きいタスク、これはもうやります。
そして、緊急ではあるんだけれども重要度が低いというタスクは、任せるということを検討してください。自分のスキルは不要だが緊急であるということです。
また、重要度が高いが緊急ではないというものは、往々にして長期的成功に関わるんだけれども期限が不明確だから緊急ではないのです。これにも取り組んでおく必要があります。
最後に、重要度が低いし緊急でもないというものは、一度検討してみる必要があります。もしかしたらやらなきゃいけないような気がしているけれども、やらなくてもいいかもしれないです。気が散るものだったり、不要なタスクだったりします。
私の判断基準
私の場合はどうやって見極めているかというと、一応タスクリストに全部、毎晩寝る前に「明日このタスクをやる」というのを洗い出します。私は午前中の4時間がメインの時間で、一番集中力も高い時間なので、そこに重要かつ緊急なタスクを入れます。
次に時間を取れるのが、午後の3時から4時ぐらいの時間です。この時間帯が、私にとっては一番集中力が低い時間なので、緊急なんだけど重要度が低い、例えばメールの返信とかチャットの返信、資料の整理なんかを入れたりします。
そして、これはやる日もやらない日もあるんですが、夜の9時から9時半か10時ぐらいまでというのは、一日の中で2番目に集中力の高い時間帯です。私にとっては、ですよ。そのときは、長期的成功に関わるが期限が不明確なタスクを入れます。例えば四半期ごとに私は計画を立てて見直し、次の四半期の計画を立てたりするんですが、そういうものをその夜の、一日の中で2番目に集中力の高い時間帯に持ってきたりします。
その順番に、私の場合は3つのブロックがあるわけなので、そこに「明日はこの時間帯にこれをやる」という割り振りをしてから寝ます。
タスクリストから消えないタスク
ところが、どうしても消えないタスクが亡霊のように残り続けます。済んだタスクはタスクリストから抜けていくんです。削除されていくので、次のタスク、次のタスク、というふうに行くんですけれども、いつまでもタスクリストから消えないタスクというのが必ず発生します。
あなたもやってみるとお分かりになると思うんですけど、緊急じゃないから手をつけないんです。だけど「なんかやらなきゃいけない気がするもの」というのが、1ヶ月とかずっと毎日そのタスクリストに残り続けるというものがあります。
ここでやっと、「もしかしてこれをやる必要がないんじゃないか」ということにそのとき気づくわけです。なので、一定期間置いてみて、タスクリストの中でずっと残るものというのは、もしかして重要度も低いし緊急ではなくて、削除できる対象なのではないか、あるいは人に任せてもいいんじゃないか、というふうに見えてくるのではないかなと思います。私はそれを判断基準にしています。
外部リソースの活用
外部リソースの活用
限られたリソースを効率的に活用するためには、外部リソースを活用することも有効です。例えば、フリーランサーやアウトソーシングを利用することで、自分の時間をより重要なタスクに集中させることができます。
フリーランスの方の活用方法
私もフリーランスといえばフリーランスなのですが、活用方法は3つあります。
- 適切なプラットフォームの選定
- 仕事内容の明確化
- コミュニケーションの維持
です。仕事の一部を人に任せられるものがあるよねという話を前述しました。どれくらいの費用をかけられるかにもよりますが、あなたのタスクのうち他人にお任せすることができるものが出てきて、予算が許せばお任せするのがお勧めです。情報発信の部分においては、私はアウトソーシングにとても助けられています。
適切なプラットフォームの選定
今の日本において継続的にタスクをお願いする場合は、いくつかのプラットフォームがあります。それぞれ使い勝手が違うので、ご自身に合うプラットフォームを選定されると良いかと思います。
仕事内容の明確化
自分の頭の中にあって自分は分かっているんだけれども、それは人に言葉にして伝えないと伝わりませんので、クラウドワーカーさんに依頼する仕事内容を明確にして、具体的な指示を出すことが非常に重要です。ここがちょっと面倒くさく感じて、「もう自分でやった方が早い」というふうに考えてしまいがちなんですけれども、綿密なすり合わせをするのは最初だけです。
例えば細かい話で言うと、私はポッドキャストで話したエピソードを、書き言葉に直してブログ投稿するのを、クラウドワーカーさんにお願いしています。そのときのルールとして、例えば、句点をどれくらいのペースで打つかとか、数字は必ず半角にする、全角は使わないとか、そういう細かい決め事を、気がついたときにお互いが共有しているドキュメントに書いていくと、具体的になりますよね。毎回毎回、細かい指示出しをしなきゃいけないとか、毎回修正をしなきゃいけないということが、どんどん減っていきます。ほとんど、丸投げに近い形でお願いできるようになり、マニュアルもできるということになります。
例えばそのクラウドワーカーさんが何かの事情で続けられなくなって、別の方にお願いするときになっても、そのマニュアルが残っていれば、「この通りにお願いします」というふうにお渡しして、また齟齬があればその都度コミュニケーションを取っていくということです。
コミュニケーションの維持
齟齬があればコミュニケーションを取るというのが「コミュニケーションの維持」にもつながるのですが、齟齬の有無に関わらず定期的にコミュニケーションを取って、進捗状況を確認するということが重要です。
この「定期的」というのをどれくらいの頻度にするかというのは、人によります。人によるというのは、発注者である自分自身の好みとか、安心できる頻度というのもそれぞれでしょうし、クラウドワーカーさんによっても、この方だったら何の連絡がなくても安心できるという場合もあれば、まだお付き合いが短い場合は、頻繁に報告していただいた方がいいという場合もありますので、一概にこの頻度でということは言えないんですけれども、お互いに安心して仕事ができる頻度でコミュニケーションを取っていく、ということが大切です。
こちらもあまり連絡しないと、クラウドワーカーさんも不安になるときがありますので、しつこくない程度に、「何か困ってないですか」とか「どこか分かりにくいところないですか」というようなコミュニケーションを取っていくと、非常にうまくいくんじゃないかなと思います。もうクラウドワーカーさんなしでは、私の情報発信は成り立っていないと断言できます。
共同作業に使える無料ツールの活用
共同作業に使える無料ツール
ここでは、無料で利用できるツールを活用することで、コストを抑えながら効率的に作業を進めることができる、いくつかの無料ツールをご紹介します。
まず最初は Canva です。Canva は、もう知らない人はいないでしょう。デザイン作成ツールです。SNS 投稿やプレゼン資料を簡単に作成できます。無料プランでもデザインの共有が可能で、例えば、クラウドワーカーさんに Instagram の投稿を外注する場合にも便利です。デザインを共有リンクを使って共有し、編集権限を付与することで共同作業ができます。
それから、Google ドライブです。ファイルの共有や共同編集に便利です。他にも、同様にクラウドで共有できるストレージはあるのですが、アカウントを持っているかとか、いろいろなことがあって、Google ドライブが一番使いやすいのではないかと思います。そして、Google ドキュメントやスプレッドシートを使って、リアルタイムで共同作業を行うことができます。これは慣れてみると非常に便利です。
私自身は元々 Microsoft 派でした。オンラインビジネスをやって10年ぐらいになるんですけれども、Google ドキュメントを使い始めたのはおそらく2020年ぐらいからなんですね。Gmail には散々お世話になってるんですが、共同作業というのが必要なかったし、Google のサービスはブラウザでやるというのが使いづらくて、オフィス365をずっと使ってきました。
ですが、チームでお仕事をする場合、ドキュメントやスプレッドシートを共有して、時には会話もしないけれども、同時に同じドキュメントの別の箇所を編集している、みたいにリアルタイムで共同作業を行うことができます。とても便利なので、お使いになってみてください。
チームコミュニケーションに役立つ Slack
それから Slack です。これはチームコミュニケーションツールですね。個人起業家にも役立ちます。フリーランサー、あるいは外部の協力者の方、もしくはコラボレーションする方と連携する際に、リアルタイムでメッセージのやり取りができます。
先日、私のコラボレーションしている方が海外に住んでいるので時差が結構あるんですけれども、「直接お話しできませんか、近々」みたいに話があったんですね。それが Slack のメッセージで飛んできたんです。私は、その週は予定が詰まっていたので、「今日、今からだったら Zoom できます」みたいな返事をしました。
その前に、彼女から「なんなら今日、今からでも私、時間空いてます」というふうに言ってくれたので、そのとき日本時間は夜で、私が「今週だった今日しかなくて、今からでも私は大丈夫です」って言ったら、「じゃあ今からやりましょう。Zoom リンクを送ります」ということで、Slack でのやり取りから Zoom でのお話にスムーズに移ることができました。それくらいリアルタイムでメッセージのやり取りができますので、無料で使える範囲には制限がありますが、使ってみられるといいと思います。
リソースの効率的な活用で、情報発信の質と量を向上させる
これらの方法を組み合わせることで、限られたリソースを効率的に活用して、情報発信の質と量を向上させることができます。これが具体的なリソースの効率的な活用法です。
まとめ
今回は、情報発信の計画と管理について、3つの重要なポイントを学びました。タイムブロッキング、優先順位の設定、外部リソースの活用でした。
タイムブロッキング
タイムブロッキングの目的は、一日のスケジュールをブロック、大きな塊に分けて計画することで、各タスクに集中しやすくなるというお話をしました。スケジュールを午前午後などのブロックに分けて、特定の作業時間を確保する。そして、例えば午前9時から11時はコンテンツ作成、午後1時から3時はSNSの投稿準備といった具合に塊で管理します。
優先順位の設定
優先順位の設定は、重要な作業を最優先で進めて効率的にタスクを管理します。
タスクリストを作成して、各タスクの重要度そして緊急度を評価します。ご自身で、恣意的に決めるということですね。重要かつ緊急、重要だが緊急ではない、緊急だが重要ではない、重要でも緊急でもないという4種類に分類して重要かつ緊急なタスクを最優先で取り組むという風に優先順位を決めることをおすすめしました。
外部リソースの活用
自分の時間をより重要なタスクに集中させるために、フリーランサーやアウトソーシングを活用するということで、ランサーズやクラウドワークス、あるいは単発のことならココナラというのも具体的にご紹介しました。そして、自分と違う人とお仕事をしていくので、仕事内容を明確にして具体的な指示を出して、定期的にコミュニケーションを取って進捗状況を確認するということは重要です。
最後に、無料ツールの活用です。コストを抑えながら効率的に作業を進めるということで、Canva、Googleドライブ、Slack をご紹介しました。
他にも似たような機能を持つツールが色々ありますので、お好みに応じて、目的に応じてお試しになってみてください。
これらの方法を実践することで計画的かつ効率的に情報発信を行っていきましょう。
次回はさらに具体的な実践方法についてご紹介します。